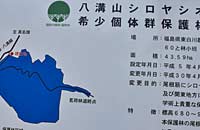◇山登り◇ 茨城県大子町 八溝山 やみぞさん:1022m  2025,4,18 訪問 爺 (あまり参考になりません) |
本当に、爺は〝ボケ爺〟である. 昨年、栃百の萬藏山に登った時、林道でイカリソウを多く見た.特に珍しい野草ではない様だけど、花の形が際立つ特徴があり、面白いが爺では中々観る事が出来ない.それが、林道を歩いてて、脇の斜面に簡単に見つけることが出来た.こんなに簡単に見つかる物なのか? その時は、栃百低山巡りをしていた為写真目的ではあまりなく、三脚は持っていかなかった.そこで三脚を持っていきしっかり撮りましょう、と、目論んだのは良いが、そこまでは結構遠い.イカリソウの生えてる所まではせいぜい登山口から10分位.わざわざ行って撮った後は時間が余ってしまう.そこで、 未だ一度しか行ってない〝栃百の八溝山〟に登って来ればいい. 八溝山は山頂まで車道があって、(爺の)登山の対象になっていない.ま、下に登山口なるものがあって車道を横断しながら登る〝登山道〟もある.が、何だかなあ・・・ で時は過ぎていた.それが、ヤマレコを見ていて、北の方(棚倉町)に一周出来るコースがあるらしい.じゃあ、イカリソウ撮影の後はそのルートで八溝山登山としましょう.で、決定 で、地図を印刷していて、あれッ、八溝山は茨城県じゃないか? 福島の棚倉町でもあるぞ! ずーーッと栃百だと思っていたのだが、、、 (下野新聞社)栃百ガイドブックを見ると八溝山は載ってない.何故、栃百だと思い込んでいたのだろうか? 答え=栃百ガイドブックより先に購入していた随想社の〝栃木の山一〇〇〟に掲載されていたのを読んでいたからである. あああ、ボケ爺だなあ・・ |
|